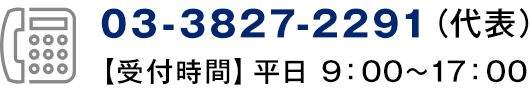著作権取得の会計的問題
第一法規「JICPAジャーナル」98年4月号
2 著作権法におけるコンピュータプログラム
著作権法は、著作物等に関して著作者の権利およびこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を 図り、 もって文化の発展に寄与することを目的としている(著作権法第1条)。同法では「著作物」を「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、 美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」(同法第2条1号)と定めている。この辺りを読む限りでは、我々が一般的なイメージとして想起する著作物とは、 文芸作品や絵画、音楽であり、時の経過により減価するものとは思えない。実際、同法第10条第1号から8号では、著作物の例示として次のものを掲げてい る。
一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
二 音楽の著作物
三 舞踏又は無言劇の著作物
四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
五 建築の著作物
六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
七 映画の著作物
八 写真の著作物
こうした著作権の体系の中に昭和60年改正で同条第9号が設けられ、「プログラムの著作物」が加えられた。さらに昭和61年改正で 第12条の2が新設され、データベースも著作物として保護されることになった。「思想や感情を創作的に表現した」ものを保護する体系の中で経済的時間的な 資源投下の成果といった産業技術的な性格のものも保護することになったのである。
コンピュータプログラムの法的保護については、新法によるのか、著作物として著作権法の中に取り込むのかという論争は、この時点で 終結したわけであり、本稿は、そうした議論を蒸し返すものではない。しかし、公認会計士・税務当局といった企業会計分野の人間にはほとんど関心のない著作 権法の世界で企業活動を支えるコンピュータプログラムに関する法改正があったのであり、また、当時は、弁護士のような法律の専門家にとっても著作権法は主 たる業務領域ではなかったのではないかと思われる。こうした経緯が一種の税務上の盲点といったものを今日もたらしているのである。
3 実務的な対応について
他社で開発されたコンピュータプログラムを買い取る取引を行った場合には、経理的にどのように対応すべきであろうか。私は2通りの方法を提案してみたい。
(1) 取得時の費用又は一定の期間で償却する
これは、著作権買い取りの対価をそのまま費用として計上するか、一定期間の経済的価値(効果)が認識できるのであれば、買い取り対 価を取得原価として著作権を計上し、経済価値を有すると認められる期間にわたって償却するものである。償却期間が客観的に決定しがたい場合には、法人税基 本通達8-1-7に準じて5年で償却するという考えもあろう。著作権買い取りという取引は、外部に開発依頼をしてソフトウェアを取得する代わりに開発依頼 しようと思ったソフトウェアがすでに存在していたから取得したのであり、類似の取引であるという解釈をするのである。
こうした経理処理は、税務上の明文規定がないために企業の経理担当者には若干躊躇される部分があるのも確かである。しかし、すでに述べたように社歌、コ マーシャルソングといった著作権買い取りの取引について損金処理が認められている以上、十分説得力がある経理処理方法であると考える。
著作権を計上しつつ、償却は実施しないでおき、当該コンピュータプログラムが経済的価値を失ったことが客観的に説明できるようになった段階で除却処理する という会計処理も考えられるかもしれない。この経理処理は、著作権の経済的価値の減少が明らかになってから一時償却することから経理処理を税務当局から否 認される可能性が低いという意味では説得力があろう。しかし、本来、経済的価値を失うまでの期間の収益と対応させることに会計的な意味があることを考える と、こうした処理は会計的には認められない。
(2) 著作権を買い取らないような契約で目的の効果を実現する
第2の方法は、著作権を取得するから償却できるかどうかの不安が生じるのであるから、著作権を買い取らずに当該著作物を自社のものであるかのように使用する方法である。
すなわち、プログラムの複製物の納入を受けてプログラム複製物の所有者となるのである。自己で使用する範囲であれば、これだけで必要な改変、複製、翻案を著作者の許諾無しに行うことができる(著作権法第20条2項、47条の2)。
また、当該プログラムの複製物を販売したり、バージョンアップをした上で販売するような自社製品同様の扱いをしたいということであれば、著作物利用許諾の 契約を著作者と結ぶことができる。通常の利用許諾では、著作権者は他の者にも利用許諾できるので、独占的利用許諾契約を結ぶことになる。
また、著作権には、複製権など譲渡の対象となりうる著作財産権と譲渡の対象とはできない著作者人格権がある。著作者人格権は、著作 者自身の人格的利益の保護を目的とするものであるから、財産権たる著作権とはその性質を異にし、一身専属性と不可譲渡性を有する(著作権法59条)*6。 例えば『吾輩は猫である』の出版の権利(複製権)は、譲渡により出版社が持つことはできても、その著作者は「夏目漱石」と表示されるという意味合いであ る。従って、利用許諾を受けるにあたっても、著作者人格権についての特約を入れないと自社の製品として売りたいのに元の制作者の名称を入れなければいけな いことになる。独占的利用許諾契約書の中で「乙(開発者)は、この契約により開発されたプログラムに関する著作者人格権を有する場合においても、甲(利用 者)及び甲の指定する者に対してはこれを行使しない」という特約条項を入れるのである。この特約条項は、著作権譲渡契約においても入れておいた方が良いと 思われるものであり*7、こうした法務知識は、ソフトウェア開発会社においては重要である。
こうした契約を締結した場合、利用許諾契約に伴う著作権利用料を支払うことになるので、経理処理は、著作権利用料を費用処理するこ とになる。契約書で一定の利用期間を定め、利用料を一括して支払った場合には、長期前払費用として利用期間に応じて均等償却することになる。また、年間支 払額を定めた場合には、その都度費用計上する。プログラムの販売本数などに比例して支払う場合には、利用料の計算期間ごとに計算された著作権利用料を費用 計上することになる。
このように著作権の買い取りによって著作権を取得することなしに、それと同等の効果を実現するという点でこの手法は興味深い。しかし、こうした取引 により生じる独占権は、委託者、受託者間の契約で定められているに過ぎないので、第三者に対してこの独占権を直接行使することはできない*8。著作権を取 得していれば、その権利は第三者に対しても当然に主張できるのであり、当該プログラムを第三者が勝手に使用している事実があれば、著作権を侵している事実 に基づき、使用差し止めの請求等ができる。しかし、利用許諾の場合、この独占権は、著作者と許諾を受けた側との間の債権契約に過ぎないので、著作者が第三 者との間でさらに無断で利用許諾契約をした場合には、その第三者に対して、自分が独占していることを主張することはできない。この意味で、著作財産権を譲 受けた場合と比較すると、立場としては弱いということになる。
したがって、(1)の著作権取得の方法を選択するか、(2)の利用許諾の方法を選択するかは、税務上ならびに経理処理上の問題と、 独占の程度が物権的か債権的かという意味での相違がある点を総合考慮して決めるということになろう。少なくとも、こうした取引が行われる前に経理部門が取 引に関与しておかないと総合考慮の余地がなくなるという点で注意が必要である。
*6 「新訂版著作権法の解説」p.48千野直邦、尾中普子著(一橋出版)1995年
*7 「ソフトウェア取引の契約ハンドブック」p.21,p.42吉田正夫著(共立出版)1989年
*8 同p.43