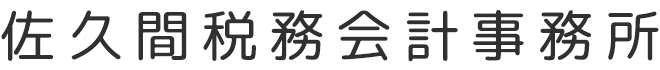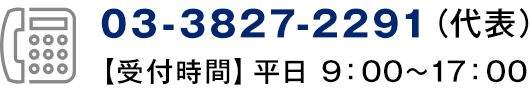外形標準課税-中小企業への影響-
納税通信・実務特集平成15年11月
1.外形標準課税の導入
平成15年度税制改正では、中小企業団体等が揃って反対していた外形標準課税が導入されました。ただし、資本金1億円超の 企業に限定されて導入されたことと平成16年4月1日以降開始する事業年度からの適用であるため、中小企業レベルでの検討はあまりされていないようです。 しかし、ベンチャー企業などでは、現在は資本金1億円未満でもその後に増資を行う可能性やストックオプションの行使での資本増加の可能性もあります。ま た、消費税の課税最低限度のように外形標準課税の適用企業規模が下がってくる可能性もないとはいえません。そこで、外形標準課税の概要とそれが個々の企業 にどのような影響を及ぼすかをまとめてみます。
2.改正の概要
(1) 対象法人
この改正が適用されるのは、資本金1億円超の大法人であり、全法人約246万社のうち、約3.1万社が対象になると言われています。
(2) 課税標準・算定方法
外形標準課税は、従来の事業税の1/4部分に適用され、3/4の部分は、所得課税であり、この分についての税率を3/4にしています。
図1 外形標準課税の概要 [現行]
![外形標準課税の概要 [現行]](../../images/200305zeimu.png)
それぞれの標準税率は、図2のとおりであり、制限税率は、標準税率の1.2倍を超えることができないとなっており、従来の1.1倍より拡張されています。
図2 標準税率
| 所得の金額 | 所得割 | 付加価値割 | 資本割 | |
|---|---|---|---|---|
| 標準税率 | 年800万円を超える金額 | 7.2% | 0.48% | 0.2% |
| 年400万円を超え年800万円以下の金額 | 5.5% | |||
| 年400万円以下の金額 | 3.8% |
付加価値割額の基準である付加価値額は、収益配分額(報酬給与額+純支払利子+純支払賃借料)±単年度損益で計算されます。また、資本割額の基準である資本等の金額は、資本の金額(または出資金額)+資本積立金額で計算されます。
3.個々の企業への影響
では、外形標準課税の導入が個別の企業にどのように影響を与えるか、説例を使って分析してみましょう。
図3 売上、損益による課税額
| 資本金2億円 | (千円) |
| ケース1 | ケース2 | ケース3 | ケース4 | ケース5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 200,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 売上総利益 | 80,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 350,000 |
| 人件費 | 25,000 | 125,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 |
| その他経費 | 40,000 | 200,000 | 75,000 | 125,000 | 125,000 |
| 営業利益 | 15,000 | 75,000 | 75,000 | 25,000 | -25,000 |
| 支払利息 | 5,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| 税引前利益 | 10,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | -50,000 |
| 事業税額(従来) | |||||
| 合計 | 684 | 4,524 | 4,524 | 0 | 0 |
| 事業税額 (改正後) | |||||
| 資本割 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 付加価値割 | 192 | 960 | 1,284 | 1,044 | 804 |
| 所得割 | 516 | 3,396 | 3,396 | 0 | 0 |
| 合計 | 1,108 | 4,756 | 5,080 | 1,444 | 1,204 |
(徴収猶予あり)
(1) 利益の小さい企業には影響大
ケース1と2を比べてみましょう。外形標準課税では、資本割などの導入の分所得割の税率が下がっています。しかし、資本金2億円に対して税引前利益が1千万円しかないようなケース1では、所得割の減税効果が資本割や付加価値割で消えてしまうことがわかります。
(2) 人件費率の影響は案外少ない
ケース2と3は売上、利益は同じでも人件費率が違います。ケース3の方が付加価値割により大きな影響を受けそうに思いますが、475万円と508万円。この程度の企業規模では、リストラして外注比率を高めるなどの企業構造の改編を求められるほどの差ではないようです。
図4 雇用安定控除の仕組み
| 雇用安定控除額 = 報酬給与額 - 収益配分額 × 70% |
報酬給与額が、報酬給与額+純支払利子+純支払賃借料からなる収益配分額の70%より多い場合には、その部分を収益配分額の計算上控除する。図3のケース3では、(250,000+25,000+0)が報酬給与額の70%の175,000を超える75,000が雇用安定控除となって、付加価値割額が計算されている。
(3) 利益が出ない企業では影響大
従来、課税所得が算出されない企業では事業税の課税はありませんでした。しかし、損益0のケース4、赤字のケース5では、100万円を超える課税が生じる ことになります。ただし、このような企業に対する措置として、対象法人が次のイ又はロのいずれかに該当すると認める場合には、都道府県知事は、その申請に基づき、3年以内の期間を限り、当該法人の法人事業税にかかる徴収金の全部又は一部の徴収猶予をすることができます。
イ 当該事業年度を含む過去の事業年度において3年以上継続して欠損法人であって、地域経済・雇用等に与える影響が大きいと認められる場合
ロ 当該事業年度において欠損法人となっている創業5年以内の法人であって、その技術の高度性又は事業の新規性などが地域経済の発展に寄与すると見込まれる場合
また、徴収猶予した期間内にその猶予した金額を納付することができないやむをえない理由があると認められるときは、その納期限からさらに3年以内の期間を限り、その徴収を猶予することができます。
(4) 企業の対応
こうした外形標準課税制度に対応するための対応は、2つに分けられます。1つは、外形標準課税の対象とならないように資本金を1億円以下にすること。もう1つは、外形標準課税の体系に沿った企業の収益構造にすることです。
たとえば、資本金1億5千万円、欠損金が7千万円あるような企業であれば、減資で欠損填補をすることで、資本金を1億円以下にしつつ、繰越損失を解消できます。なお、税務上の繰越欠損金は変動しません。あるいは、資本金8000万円の企業が直接金融で資金調達する場合、4000万円の増資でも2000万円を資本準備金にする、あるいは増資ではなく新株予約権附社債にするといった工夫ができます。しかし、資本割額を減らすために4億円の資本金を2億円に無償 減資するといったことは無意味です。無償減資では、減少した資本金相当額が資本積立金となり、資本金+資本積立金で算出される資本割額は、減少しないからです。あくまで資本金を1億円以下にしなければなりません。
また、企業グループの中で資本金の大きさに比較して利益規模が少ない企業があれば、他の会社が吸収合併したり、逆に他のグループ会社の事業を営業譲り受けることでグループ全体での外形標準課税額を検討することもできるでしょう。リストラなどで給与体系の再構築を目的として資本金1億円以下の新会社に全従業員を移籍して、そこからの出向という形式で事業を行う場合には、結果として外形標準課税を避ける効果が生じます。